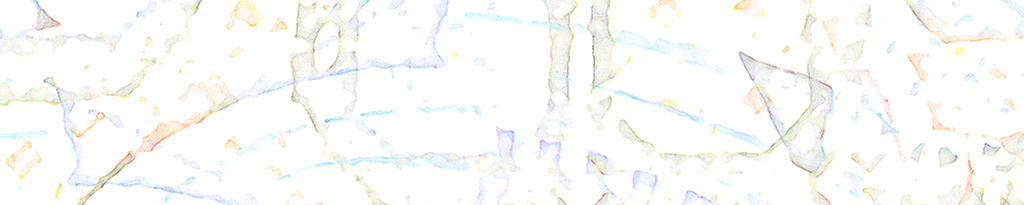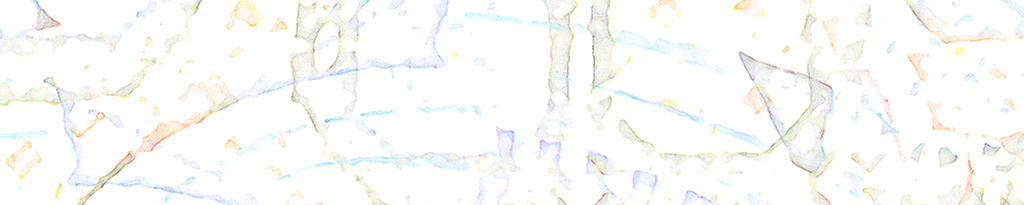
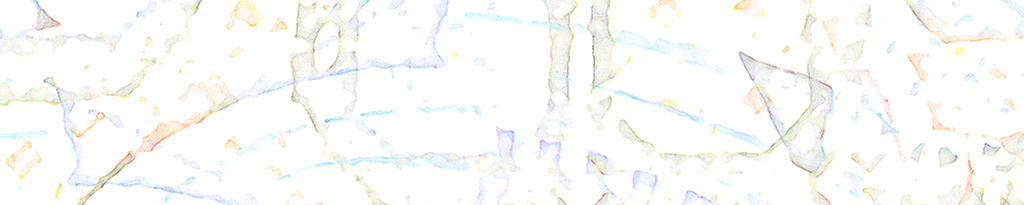
|
凛と鈴が鳴った様に彼女は云った。とうの昔に散ってしまった桜の木を見上げ、口元だけを緩めて笑う。ぴんと筋が張りつつもか細いその声はざあざあと云う風の音に容易くかき消された。其れを彼女は気にしなかった。一言足りとも彼女の言葉を聞き逃したくなかった僕は、見えぬはずの風を睨んで、そして空を見上げてから照り付ける太陽を憎んだ。彼女はそんな僕を見て、微笑った。 「夏の海へ行きたいのです。波の音は美しいのでしょうね。聞いたことはありませんが」 ああ、貴方に頂いた貝殻を通してなら、聞きましたね。唇を震わせて彼女は音を紡いだ。鈴の音のような声が縦糸となり、緩やかに動く唇が横糸となる。一つになった柔らかな音は確かに僕の耳に吸い込まれていった。 あの時渡した貝殻を彼女は覚えていてくれた。その事実が胸を騒がせる。なら、海へ行こう。僕は紡がれた糸を織る様に、思いの丈を籠めた声で告げた。 「ありがとう、ダイゴ。夏が楽しみだ」 彼女はそう云って、今にも儚くも鮮やかに消えてしまいそうな笑みを浮かべた。 「もう、蝉が鳴くでしょうね。きっとけたたましい音なのでしょう。両の耳の中を突き破り、そして通り抜ける様な音なのでしょう。ああ、聞いてみたかった」 困ったように眉を下げ、あからさまにふうと溜め息を吐く。どう足掻いても、どんなに策を講じても蝉の声が聞けぬのは彼女も承知していること。季節は早くも来ないし、ゆっくりにもならない。だが、必ず遣って来る。何も変わらない。 一度だけ彼女に聞いたことがある。季節を守らなくともいいのではと。春に花火をしようが、秋に花見をしようが、自由ではないかと。しかし彼女は云った。人為的なものはつまらぬだけだと。私の眼は、偽りの現状を見る為でなく、四季の移ろいを観る為に在るのだと。 「ダイゴ、夏が来ますよ。早いものです。貴方と見上げた桜は綺麗でしたね。今はもうあの木は緑に染められていますが、次に会うときはきっとまた薄紅で包まれているでしょうね。散り逝く様は胸が締め付けられますが、それもまた美しいのでしょう。ああ、楽しみです」 瞳を伏せた彼女はとうの昔に散ってしまった桜の様に儚く、それでいて美しい笑みを僕に見せた。幾度となく、そう数えきれぬ程見たであろうその笑顔はどうしてか久しぶりに見たように感じた。 もうすぐ彼女は彼女であって彼女じゃない誰かになってしまうのだろう。桜を慈しみ、広い海に想いを馳せる彼女ではなく、散り行く紅葉を憐れに思い、それでも美しいと囁く彼女になるのだろう。 それならば、次の季節の私に、どうぞ宜しく。 あの日から幾年経っただろう。君と出会ってからどれほどの年月が流れただろう。もうはっきりとは思い出せないあの時に想いを馳せる。ああ、夏が遣って来る。季節が変わる。四季がまた彼女を拐ってゆく。巡る春夏秋冬を恨む僕を置いて、空っぽの彼女だけをただ残して。 それでも、何度年月が流れたって、何度季節が巡ったって、何度君が僕を忘れたって、僕はずっと君の手を引いて歩くよ。 2011/10/23 |